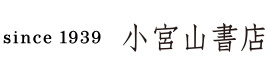−昨年夏に開催した初個展から一年あまりが経ちました。製作に関して何か変化はありましたか?
製作そのものにあまり変化はありませんが、在廊中にお客様と直接お話しできたことはとても大きな経験でした。作品に触れた時の表情や手つき、丁寧に扱ってくださる姿を目の前で見て、「このまま続けてもいいのかもしれない」という自信をもらった気がします。
陶芸は歴史が長いこともあり、それを学術的に評価する人や探求する人も多く、陶芸家を取り巻く環境には時より何となく厳格で重々しい空気が漂うことがあります。私は、作品に触れた人の気持ちが少しほっとするような、思わずふと笑ってしまうようなものを作りたいという想いで製作をしているので、厳格なイメージからは遠く、皆に受け入れられるものではないかもしれませんが、実際に手にとる方々を見たことで自信に繋がったのだと思います。率直な感想や質問いただく内容も、自分自身にとっては新しい感覚や発見が多く、楽しかったです。
−「陶芸家」という言葉が出ましたが、陶芸家は「工芸」とも密接な関わりがあると思います。ご出身地の石川県は、豊かな文化土壌で九谷焼や輪島塗などの工芸が発展し根付いている土地ですよね。ご自身の作品と「工芸」という言葉をどのように捉えていますか?
私の中では、自分の作品は「工芸」だと思って製作しています。素材と技法に対するリスペクトと、自分の作りたい、表現したいという想いとが同じバランスであって作品になることが「工芸」だと捉えているので、私の創作の基本は工芸にあります。色々な素材や手法がある中で、何をどう使うことが自分の表現したいことにとって最適か、探して試し続けて今の形があるのだと思っています。先日も、金沢の国立工芸館で開催中の「ルーシー・リー 展」に行ってきましたが、大好きなルーシー・リーの作品も、自分の作品とは輪郭も質感も大きく異なります。彼女の作品そのものはもちろん、表現したいことと素材や技法がぴったりと合っている必然性のようなものにも惹かれているのかもしれません。工芸に限らず、自分の想いを文章で表現することや絵の具で表現することにおいても、それぞれ共通するものだとは思いますが。

−言恵さんは、よく本を読まれますね。最近はどのような本を読んでいますか?
最近は、考古学に興味があるので関連書籍を読み漁っています。それと並行して、『古事記』や『風土記』も読んでいます。考古学は、かつて捏造事件(!)などもありましたが、基本的には出土品から読みとれる事実を記しているので、その記録と併せて、当時の人の意識や考え方が反映されている書物を読むと、より立体的に捉えられて楽しいです。
本を読んでいると、考古学は本当にすごいと思い知らされます。大昔のことでも研究が進み明らかになる事実がたくさんありますし、一方で決して分かり得ないこともやはりたくさんある。例えば、縄文土器を作ったのは、どんな人だったのか、何を考えながら手を動かしたのか。そうした、分からない余白部分があるからこそ、あれこれ自由に想像を膨らませることができて、ワクワクするのだと思います。
陶芸の歴史は本当に長く、各地で独自に発展しているので資料も多いですし、自分なりに探求できるところも好きです。私は土や石を扱うので、鉱物学の本も読みます。石の本はもともと好きですが、地学教師であった宮沢賢治(みやざわ・けんじ)の地学にまつわる本もおもしろいですよ。
−小宮山書店の中で、気になるフロアはありますか?
どのフロアも気になりますが、版画も好きなので中2階が特に気になります。文学では三島由紀夫(みしま・ゆきお)の作品を中心に置いている場所だと思いますが、川上澄生(かわかみ・すみお)や武井武雄(たけい・たけお)の書籍も豊富にあって、見応えがあります。特に武井武雄については、名前は知っていましたが実際の本に触れる機会はなかったので、木版画や銅版画、そのほか様々な素材と技法をこれでもかと駆使して一冊一冊本を作っていることに驚きました。素材と技法、それにぴったりの物語を自身で作り、139冊の本という形に残した気迫ある偉人の一人ですよね。
−本は、製作の合間に読むことが多いのだと思いますが、製作にあたり何かルーティーンのようなものはありますか?
まずは、まとめて時間を作ってから取り掛かるようにしています。陶芸には、土作りや乾燥など工程があるので、自分の都合よりも土の都合を考えて製作します。さらに、動物など生き物を作るときに使う「磁土」と、植木鉢の土台部分や今回も登場した壺などに使用する「陶土」は、混ぜると変質してしまうので、どちらかを作るときには道具も作業台もしっかり拭いて綺麗に整えてからスタートします。
−言恵さんの作品から感じる清涼感や凛とした神聖な空気感の源にそうした細やかな作業があるのですね。例えば作品を購入した方にとって、それがどのような存在であってほしいと思いますか?
好きなように楽しんでいただけたらと思いますが、たとえ隅の方でも、生活の中にふとある存在であったらいいなと思います。作品はもちろん自分が表現したいことを形にしているのですが、自分の意思や主張をそのまま示したいというよりも、持った人の世界が広がるような、余白のあるものを作りたいと考えています。先日、自分自身が表に出て表現をするミュージシャンが度々小宮山さんのところで私の作品を買ってくださると伺ったときも、そういったことが背景にあるのかなと思いました。

−最後に、これから作ってみたいものはありますか?
たくさんあります!本を読んでいると、色々な世界を想像して妄想が膨らみます。もちろん本だけではなく、友人とお喋りしたり海沿いを歩いたり、山に登ったり、日常の小さなことから沸々と湧き出るものが、土を触っているうちに形になるので、自分でもどんなものが出来上がるか、また焼き上がってどんな変化が起こるかも含め、いつもワクワクしながら創作しています。
−ありがとうございました。いよいよ個展会期最後の週末ですね!
最後の週末も在廊するので、色々なお客様にお会いすることを楽しみにしています。自由に作品を見て触れていただけたら嬉しいです。
2025年10月
村田言恵 個展「Mellow Ceramics ⅱ」
会期:2025年10月17日(金)〜11月2日(日)
会場:小宮山書店中三階
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7
お問い合わせ
KOMIYAMA TOKYO G
03 6811 7355 または 03 3291 0495(小宮山書店)
作品は、会期中から会期終了後も弊社ウェブサイトにて掲載、販売をしております。
https://www.book-komiyama.co.jp/booklist_feature.php?feature=539
ご不明点等ございましたら、上記お問い合わせのメールアドレス、または電話番号までお気軽にお問い合わせください。
KOMIYAMA TOKYO